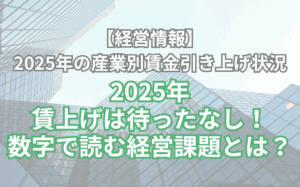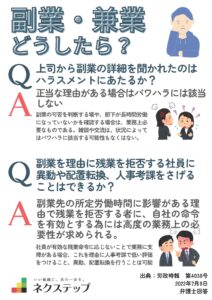もしも従業員が「休職」になったら
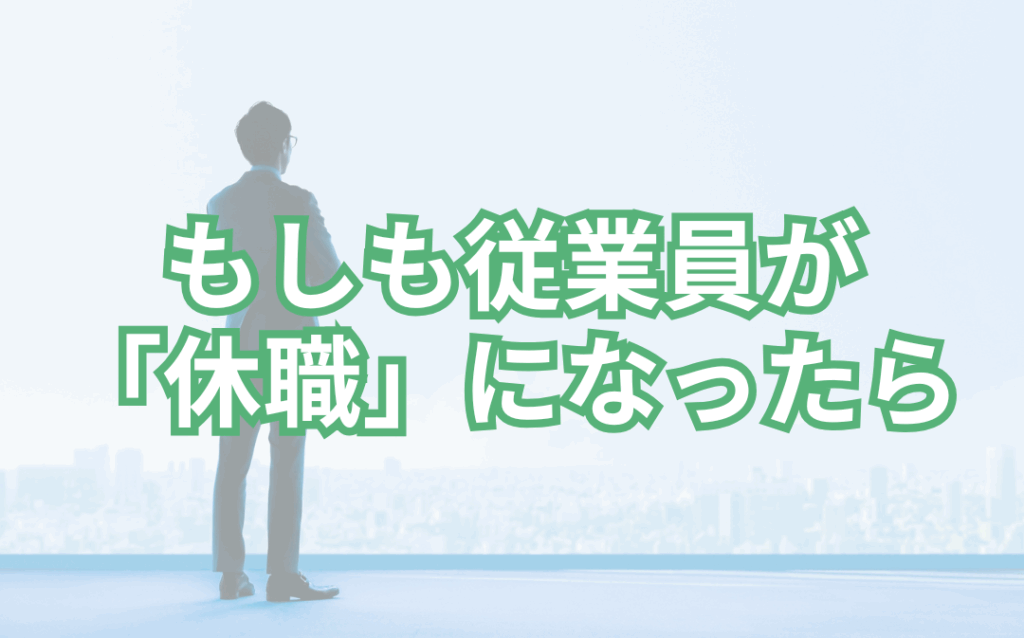
クライアントから寄せられる相談のトップ3に入るのが、メンタル不調などによる「休職」対応です。
人間である以上、症状も状況も一人ひとり異なります。特に初めて従業員から連絡を受けた経営者や人事担当者の皆さまは、「どう対応すればいいのか」と途方に暮れることも少なくありません。
私自身もこれまで数えきれないほどのご相談を受けてきましたが、最近の増加傾向を見ると、これは大きな社会的課題であると感じています。
そこで今回は、休職の考え方と対応のポイントをご紹介します。
休職制度の基本的な考え方
会社には事業の目的があり、組織はそれを達成するための機能体です。したがって雇用契約には「権利と義務」が存在します。
従業員が健康に働き、役割を果たすこと、その対価として会社は賃金を支払っています。ですから、体調管理もまた仕事をする上で欠かせないスキルの一つといえるでしょう。
厳密に言えば、メンタル不調で長期にわたり働けないことは契約違反と捉えることもできます。とは言っても、長い職業人生の中で心身が不調になることは誰にでも起こり得ます。だからこそ会社は、法的に義務づけられていない「休職制度」を就業規則の中に設け、心身を整える猶予期間を与えているのです。
休職は「復帰のために心身を整える期間」
再び元気に働けるよう、安心して療養に専念してもらうための制度なのです。
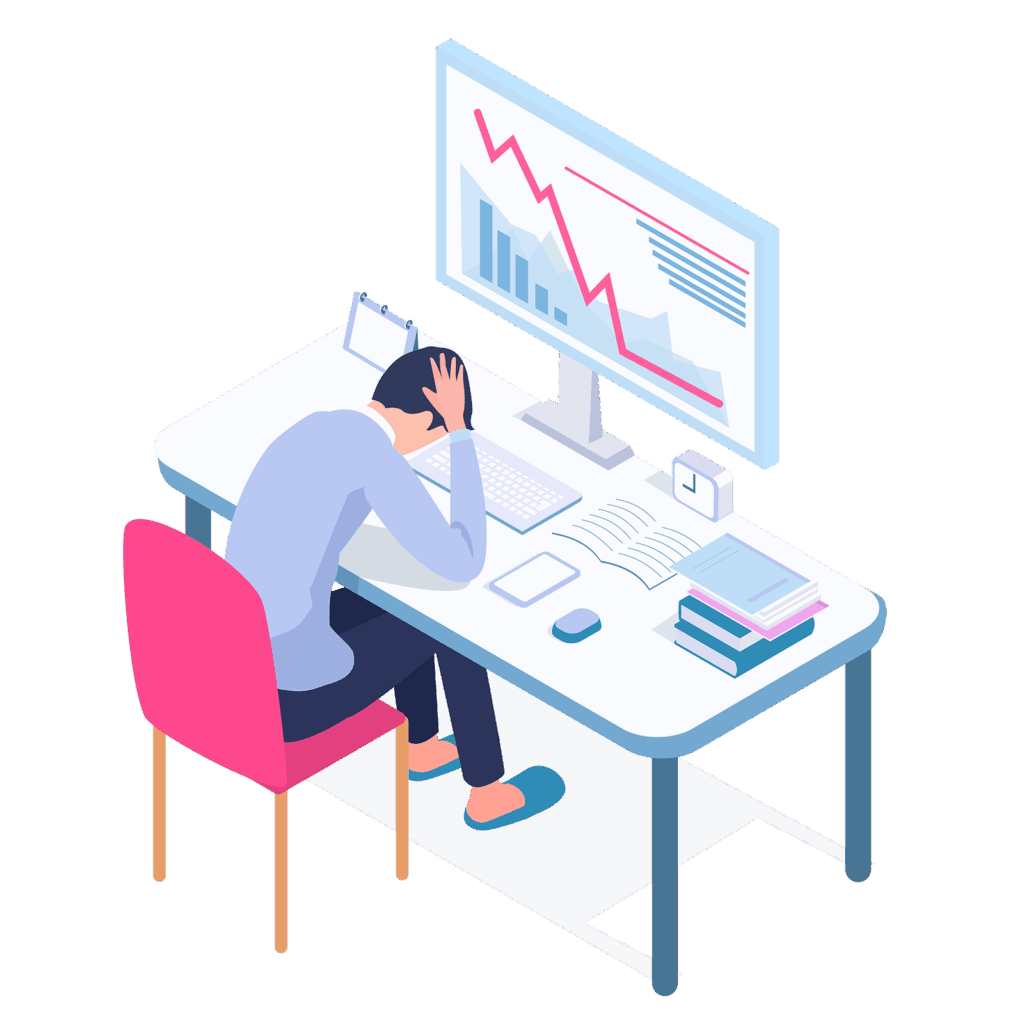
復帰に向けた第三者の活用
案件によっては、職場環境や人間関係が背景となり、不調が長引くこともあります。ハラスメントが関わるケースも決して少なくありません。
そうしたときには、社内だけでの対応では限界があります。
社労士(もちろん!)、弁護士、産業医など、第三者の専門家を交えることで客観的な視点から解決の糸口を見つけることができます。ぜひ専門家にご相談ください。
その際に重要となるのが、会社として「それまでどのような対応をしてきたのか」を示すための記録やプロセスです。会社が誠実に取り組んできた証拠となり、第三者が正確に状況を把握する助けにもなります。
本当に大切なのは「予防」
休職対応マニュアルは一度つくって終わりではなく、運用を通じてブラッシュアップし、自社オリジナルのものに育てていくのが理想です。もちろん、実際に使うことがないのが一番ですね。
予防として欠かせないのが、日常的なコミュニケーションです。
挨拶でも、声掛けなど短い時間でも構いません。回数を増やすことで小さな変化や違和感を見逃さず、気軽に声をかけやすい仕組みをつくることが大切です。職場の特性を活かしてぜひ取り組んでみてください。
おわりに
「休職対応マニュアル」はもしもの時に備える羅針盤です。 経営者や人事担当者の皆さまが安心して対応できる体制づくりを、これからもご一緒に考えていければ幸いです。