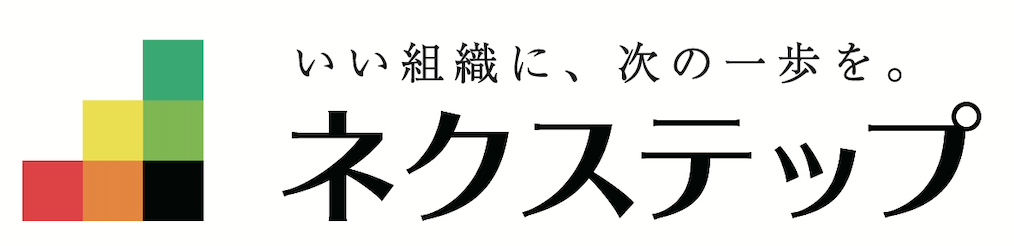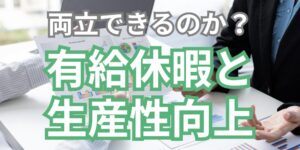2025年4月施行 育児・介護休業法改正のポイント解説

1.育児休業に関連すること
(1) 子の看護休暇の取得要件が拡充
【変更点】
- 対象が小学校就学の始期に達するまでから小学校3年生修了までに拡充
- 取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園(卒業)式が追加
- 労使協定で継続雇用期間6ヶ月未満の従業員を除外していた場合は撤廃
【対応のポイント】
対象者や事由は拡充となりますが、取得日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)、1日と時間単位の取得可能、無給・有給にするかは企業の選択であることに変更はありません。
(2) 残業免除の対象拡大
【変更点】
所定外労働(会社が定めた労働時間)を超える残業に対して免除を請求できる対象従業員が、3歳未満の子を養育する従業員から小学校就学前の子を養育する従業員に変わります。
【対応のポイント】
労働時間管理や周囲の理解が必要です。請求のための様式も整えて請求しやすい環境を整えましょう。
(3) 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
【変更点】
インターネット等で一般の方が閲覧できるように公表する義務が、従業員数1,000人超から300人超の企業に変わります。
【対応のポイント】
育児休業取得状況を年1回、事業年度の終了後概ね3ヶ月以内に公表するよう計画を立てましょう。

2.介護休業に関連すること
(1) 介護離職防止のための雇用環境の整備
【変更点】
従業員の介護休業や介護との両立を支援するため、以下のいずれかを 必ず 実施する必要があります。
【企業が選択できる4つの措置】(いずれか1つ以上が必須)
- 介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度に関する相談窓口の設置
- 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度の取得事例の収集・提供
- 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知
【対応のポイント】
上記の4つからなるべく複数の措置を自社でできうる範囲で対応し、周知しましょう。
(2)介護離職防止のための 個別周知と意向確認等
①介護に直面した旨を申出した労働者に対する個別の周知・意向確認
【変更点】
企業は 介護休業の申し出をした従業員に対して、個別に周知し、取得の意向を確認する義務 があります。※取得や利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
【周知事項】
介護休業に関する制度・介護両立支援制度等の内容や申し出先、介護休業給付金についてを周知・意向確認します。
【個別周知・意向確認の方法】
面談(オンラインも可)、書面交付、FAX、電子メール等
【対応のポイント】
従業員が相談・申出しやすい職場環境を整えましょう。
②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
【変更点】
従業員が40歳に達する日の前後1年間の間に①の周知事項の情報提供を行わなければなりません。
【対応のポイント】
介護保険料徴収開始の対象者を把握して、周知できるように労務管理を行いましょう。

3.その他
育児との両立支援のために2025年4月から新たな給付金が用意されます。
①出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金 は、育児休業を取得した際に一 定の条件を満たすことで支給される給付金で、子育てのスタートを経済的にサポートするための制度です。
②育児短時間給付金
育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
まとめ
育児・介護休業法の改正について、「うちの会社は関係ない」と思っていると、知らない間に法令違反になってしまったり、従業員との信頼関係を損ねてしまう可能性もあります。
しかし、難しい対応は必要ありません。
「相談窓口の設置」や「社内での制度周知」 など、簡単な取り組みから始めることができます。
企業がしっかり対応すれば、
・従業員の働きやすさ向上
・職場定着率アップ
・企業のイメージ向上
につながります。
ネクステップでは、今回の育児・介護休業法改正に対応するための「就業規則」の改定に加えて、職場環境を整えるための支援パッケージをご用意いたしました。
この機会に最新情報にアップデートを行いませんか?